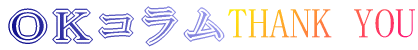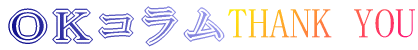گك•ھ‚ج“ْ‚ةƒRƒ“ƒrƒj‚ةچs‚‚ئŒb•ûٹھ(ٹھ‚«ژُژi)‚ھ
”„‚ء‚ؤ‚¢‚éŒُŒi‚ً‚و‚–ع‚ة‚µ‚ـ‚·‚ھپA‚ب‚ٌ‚إگك•ھ‚ج“ْ‚ة
Œb•ûٹھ(ٹھ‚«ژُژi)‚ًگH‚ׂé‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH
Œb•ûٹھ‚ة‚ـ‚آ‚ي‚éگg‹ك‚ب‹^–â’²‚ׂؤ‚ف‚ـ‚µ‚½‚إ‚·پB
‡@‚ب‚؛ٹھ‚«ژُژi‚جژ–‚ًŒb•ûٹھ‚ء‚ؤŒ¾‚¤‚جپH(ŒêŒ¹پE—R—ˆ‚حپH)
چ‘Œأ‘م‚ج‰ؤ(‹IŒ³‘O2000”N-‹IŒ³‘O1600”N)پA
ںu(‹IŒ³‘O17گ¢‹I-‹IŒ³‘O1046”N)‚جژ‘م‚©‚çپA
‰A—z“¹پi‚¨‚ٌ‚ف‚ه‚¤‚ا‚¤/‚¢‚ٌ‚و‚¤‚ا‚¤پj‚ئ‚¢‚¤ژv‘z‚ھ‚ ‚èپA
‚»‚ج”N‚ج•ں“؟‚ًژi‚éچخ“؟گ_پi‚ئ‚µ‚ئ‚‚¶‚ٌپA‚ئ‚ٌ‚ا‚³‚ٌ)‚ھ
‚ ‚é•ûٹp‚ة‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤ژv‘z‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ج
چخ“؟گ_—l‚ھ‚¢‚é•ûٹp‚ًŒb•û(‚¦‚ظ‚¤)‚ئ‚¢‚¢پA‚»‚ج•ûٹp‚ةŒü‚©‚ء‚ؤ
ژ–‚ًچs‚¦‚خ–œژ–‚ة‹g‚ئ‚ب‚é‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB
‚±‚جژv‘z‚ھ“ْ–{‚ة“`‚ي‚èپAŒb•û‚ةŒü‚©‚ء‚ؤٹھ‚«ژُژi‚ً
گH‚ׂéژ–‚©‚çŒb•ûٹھ‚ئŒ¾‚ي‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB
پ¦‰A—z“¹‚ئ‚حپEپEپEژ©‘RٹE‚ج–œ•¨‚ح‰A‚ئ—z‚ج
“ٌ‹C‚©‚çگ¶‚¸‚é‚ئ‚·‚éژv‘z‚إ‚·پB
پ¦چخ“؟گ_—l‚ھ‚¢‚é•ûٹp‚ة‚آ‚¢‚ؤپEپEپE
| گ¼—ï‚ج1‚جˆت |
Œb•û‚ج•ûٹp |
| 0پA5 |
گ¼“ىگ¼ |
| 1پA6پA3پA8 |
“ى“ى“Œ |
| 2پA7 |
–k–kگ¼ |
| 4پA9 |
“Œ–k“Œ |
‚±‚ج‚و‚¤‚ةچخ“؟گ_—l‚ھ‚¢‚é•ûٹp‚ح–ˆ”NŒˆ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
‡A‚ب‚؛ٹھ‚«ژُژi‚ب‚جپHپE‚¢‚آ‚©‚çگH‚ׂé‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚جپH
‚ب‚؛پE‚¢‚آ‚©‚çٹھ‚«ژُژi‚ًگH‚ׂé‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚©پH
‚ج–¾ٹm‚ب——RپEژٹْ‚ي‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAˆب‰؛‚جگà‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB
‡@‘هچم‘Dڈê‚ج’U“كڈO‚ھگك•ھ‚ج“ْ‚ةچs‚ء‚ؤ‚¢‚½پA
—Vڈ—‚ةٹھ‚«‚¸‚µ‚ًپuٹغ‚©‚ش‚èپv‚³‚¹‚é—V‚ر‚©‚çژn‚ـ‚ء‚½‚ئ‚·‚éگà
‡Aچ]Œثژ‘م‚جڈI‚ي‚èچ پA‘هچم‚جڈ¤گl‚½‚؟‚جڈ¤”„”ةگ·‚ئ–ï•¥‚¢
‚جˆس–،چ‡‚¢‚إپA—§ڈt‚ج‘O“ْ‚جگك•ھ‚ةپuچK‰^ٹھژُژiپv‚جڈKٹµ‚ھ
ژn‚ـ‚ء‚½‚ئ‚³‚ê‚éگà
‡Bچ]Œثژ‘م––ٹْ‚©‚ç–¾ژ،ژ‘مڈ‰ٹْ‚ة‚¨‚¢‚ؤپA
‘هچم‚جڈ¤گlپiپu‘Dڈê‚جڈ¤گlپv‚ئ‚·‚éژ‘—؟‚à‘¶چف‚·‚éپj
‚ة‚و‚éڈ¤”„”ةگ·‚ج‹Fٹèژ–‚ئ‚µ‚ؤژn‚ـ‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤گà
‡C–LگbڈG‹g‚ج‰ئگbپE–x”ِ‹gگ°‚ھ‹ôپXگك•ھ‚ج‘O“ْ‚ة
ٹC‘غٹھ‚«‚ج‚و‚¤‚ب•¨‚ًگH‚ׂؤڈoگw‚µپA
گي‚¢‚ة‘هڈں—ک‚ًژû‚ك‚½ژ–‚©‚çگ¶‚ـ‚ꂽ‚ئ‚·‚éگà
‡D1800”N‘م‚ج‚ ‚é”N‚جگك•ھ‚ج“ْ‚ةپA
‘هچم‹كچx‚جگ\‘؛‚ةڈZ‚قکVژل’jڈ—‚ھڈW‚ـ‚èپA
ٹھژُژi‚ًگH‚·ژ‚ةپAگط‚è•ھ‚¯‚éژèٹش‚ًڈب‚‚½‚ك‚ة
ˆê–{ٹغ‚©‚ش‚è‚ً‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھ”ڈث‚¾‚ئ‚·‚éگà
‚±‚ج5‚آ‚جگà‚ًŒ©‚éŒہ‚èپA’x‚‚ئ‚à1900”N‘م‘O”¼‚ة‚ح
‘هچم‚إ‚حŒb•ûٹھ‚ًگH‚ׂéڈKٹµ‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئŒ¾‚¦‚ـ‚·پB
‡BŒb•ûٹھ‚ًگH‚ׂéڈKٹµ‚ح‚¢‚آ‚©‚ç‘Sچ‘‚ةچL‚ـ‚ء‚½‚جپH
Œb•ûٹھ‚ًگH‚ׂéڈKٹµ‚ح‘هچم’n•û‚©‚ç‘Sچ‘‚ضچL‚ـ‚è
‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚¢‚آچ ‚©‚ç‘Sچ‘‚ةچL‚ـ‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH
‚±‚ê‚حپA1998”N‚ةƒZƒuƒ“-ƒCƒŒƒuƒ“‚ھŒb•ûٹھ‚ً
‘Sچ‘””„‚µ‚½ژ–‚©‚çچL‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚µ‚½پB
‚»‚جŒمپAŒb•ûٹھ‚ج”F’m“x‚ح‚à‚ج‚·‚²‚¢گ¨‚¢‚إچL‚ـ‚è
2006”Nپi•½گ¬18”Nپj‚ة‚ح”F’m“x‚ھ92.5%‚ة‚à
‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB(ƒ~ƒcƒJƒ“‚ج’²چ¸‚ة‚و‚é‚à‚جپB)
‡CŒb•ûٹھ‚ج‹ï‚ح‰½‚ھ“ü‚ء‚ؤ‚¢‚é‚جپH
ƒXپ[ƒpپ[‚âƒRƒ“ƒrƒj“™‚إ”„‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éŒb•ûٹھ‚إ‚·‚ھپA
‹ï‚ح‰½‚ھ“ü‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH
ژہ‚حپA‘¾ٹھ‚«‚ة‚ح7ژي—ق‚ج‹ïچق‚ًژg‚¤‚ئ‚³‚êپA
‚»‚جگ”ژڑ‚حڈ¤”„”ةگ·‚â–³•a‘§چذ‚ًٹè‚ء‚ؤ
ژµ•ںگ_‚ة‚؟‚ب‚ٌ‚¾‚à‚ج‚إ•ں‚ًٹھ‚«چ‚ق‚ئˆس–،•t‚¯‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
‚µ‚©‚µ‚ب‚ھ‚çپA7ژي—ق‚ج‹ïچق‚حŒˆ‚ـ‚ء‚ؤ‚¨‚炸پA
‚©‚ٌ‚ز‚ه‚¤پEƒLƒ…ƒEƒٹپEƒŒƒ^ƒXپE‚©‚¢‚ي‚êپEƒVƒCƒ^ƒPژدپE
Œْڈؤ‚«—‘پEƒEƒiƒMپiƒAƒiƒSپjپEچ÷‚إ‚ٌ‚شپi‚¨‚ع‚ëپj‚ب‚ا‚ھ
—p‚¢‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ¦ژµ•ںگ_‚ئ‚حپEپEپE•ں‚ً‚à‚½‚ç‚·‚ئ‚µ‚ؤ“ْ–{‚إ
گM‹آ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éژµ’Œ‚جگ_‚جژ–‚ًŒ¾‚¢‚ـ‚·پB
ژµ’Œ‚جگ_‚ئ‚حپAŒb”نژُپA‘هچ•“VپA”ùچ¹–ه“VپA
•ظچث“VپA•ںک\ژُپAژُکVگlپA•z‘ـ‚جژ–‚ًŒ¾‚¢‚ـ‚·پB |