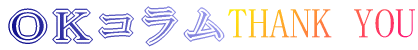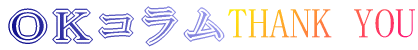11月23日は「勤労感謝の日」と呼ばれ、祝日に指定
されていますが、なぜ勤労感謝の日は11月23日なので
しょうか?・またどんな趣旨があるのでしょうか?
早速、勤労感謝の日に関する身近な疑問を調べてみました。
①なぜ勤労感謝の日は11月23日なの?(歴史・由来)
古来から日本では、勤労感謝の日の起源である、
農作物(五穀)の収穫を祝う風習がありました。
飛鳥時代(592年-710年)になると、
皇極天皇(こうぎょくてんのう-594年-661年)は
皇居宮中内で五穀を天神地祇(てんじんちぎ)に進め、
天皇自らもそれを食す事で、その年の収穫に感謝する
新嘗祭(にいなめさい)という行事を行うようになりました。
一時、中断される時期もありましたが、
元禄時代(1688年-1704年)の東山天皇(1675年-1710年)
の在位に復活しました。この行事は1873年(明治6年)の
太陽暦採用以前は旧暦の11月の2回目の卯の日に
行われてきました。その後、1873年に太陽暦(グレゴリオ暦・新暦)
が導入された年は、11月の2回目の卯の日(11月23日)
に行われ、1874年からは毎年、11月23日に行われるように
なりました。その後、新嘗祭の日は、第二次世界大戦の敗戦により
1948年、「勤労感謝の日」という名前に改められました。
つまり、「勤労感謝の日」は、以前は「新嘗祭」であり、
それ以前は、農作物(五穀)の収穫を祝う行事だったんですね!!
※五穀とは・・・日本では、米・麦・
粟(あわ)・豆・黍(きび) または稗(ひえ)の事を指す事が多いです。
特に五穀の内容は決まってません。また、五種をブレンドした米を
五穀米といいます。(健康志向の人には大人気ですね。)
※天神地祇とは・・・
天地の神々、すべての神々の事を指します。
※卯の日とは・・・
子(ねずみ)・丑(うし)・寅(とら)・卯(うさぎ)・辰(たつ-りゅう)・
巳(み-へび)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・
戌(いぬ)・亥(いのしし)の十二支を日付ごとに
割り付けた時に該当する日の事を言います。つまり、
卯の日は月に2~3回あります。
②勤労感謝の日にはどんな思いが込められているの?(趣旨)
勤労感謝の日は、祝日法によると、
「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう日」との
趣旨が書かれています。「たつとび」とは、重んじる・尊重するという
意味があります。つまり、勤労感謝の日は、
「私達の日々の仕事に感謝する日」だったんですね。
勤労感謝の日には国民全員が一生懸命働き、助け合う
社会に感謝してみてはいかがでしょうか?
③なぜ「新嘗祭」から「勤労感謝の日」という名前に変わったの?
農業中心の時代には、農作物の収穫を祝う行事は
とても大事にされてきましたが、時代が進むにつれ、
農業だけでなく産業や色々なサービス業も誕生した事から
「新嘗祭」から「勤労感謝の日」へ名前が変更される事になりました。
産業の発展によって農業・産業・サービス業等をすべて含む
「労働」という言葉が使われるようになったんですね。
ちなみに、「新嘗」とはとはその年収穫された新しい穀物のことを指します。 |